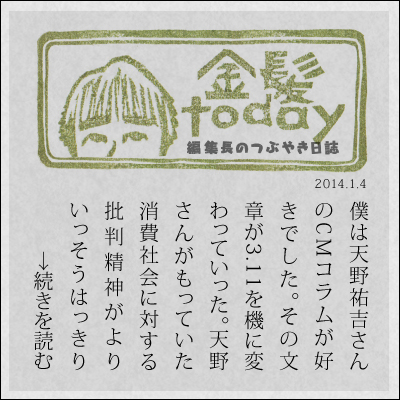PROFILE【湯浅 誠】社会活動家。東京大学法学部卒。2008年末の年越し派遣村村長を経て、2009年から3年間内閣府参与に就任。内閣官房社会的包摂推進室長、震災ボランティア連携室長などを歴任。著書に『ヒーローを待っていても世界は変わらない』『反貧困』『岩盤を穿つ』『貧困についてとことん考えてみた』など多数。公式サイト/http://yuasamakoto.org/
聞き手:山田エイジ/構成:松澤有紗
支援しているつもりはないです。自分のためにやっている。
山田
湯浅さんが社会活動家をはじめたきっかけを教えていただけますか?
湯浅
阪神大震災が起こった1995年に、友達がホームレス支援をやっていまして、私がその活動を見に行ったことが一番初めの経緯ですね。偶然みたいなものです。
山田
その時、どういう気持ちに?
湯浅
なんか、知っちゃったな、という感じですかね。知らなかったらよかったとは、思わなかったですが、あんまり知ってうれしいこともないんだけど、知ってしまったことは、なかなか知らないことにはできないな、という感じですか。
山田
知ってしまった、というのをもう少し具体的に言うと?
湯浅
渋谷のセンター街で、ハンバーガーとかを集めているホームレスの人がいます。あるいは東急の109の下の、地下鉄とつながっている地下のところで寝ている人がいる。私は渋谷には飲みにいくことはあっても、活動で行く事は、当たり前ですけど、それまではなかった。そうしたら、そこに人がいるわけですよね。
ちょっとなんというか、変な感じですよ。前からそこは通ったことがある、その時にもこの人達はいたはずだ、だけど、全く自分の記憶に残っていない。見た覚えがない。それは多分、自分の中に問題意識がないと、きっと視界に入っても脳みそまで届いていないというか、居ても、居たという認識を持たないで帰っている。
そういう意味で、人間って、見たいものしか見ていないんだな、というか、自分にとって居心地の悪いものとか、出来ればあまり見たくないものとかは、見なかったことにして過ごしているんだな、ということが、よくわかっちゃったという意味でショックでしたね、あの経験は。
山田
友達に連れていってもらって、その後どういう展開に?
湯浅
2、3年はね、すごいいい加減な関わり方で、行ったり行かなかったりと、多分あの頃一生懸命やっていた人からすると、『なんかあいつ、あてになんねぇな』という感じだったと思います。
ただ、だんだん、だんだん、変わって来ちゃったのは、2〜3年経った98年ぐらいで、なんというか、循環が始まっていくというか、つまり、ちょっと頻繁に行くようになると、こっちも相手の名前を知ってしまうし、向こうもこっちの名前を覚えてしまうということが起こりますよね。
すると、ホームレスのおっちゃんじゃなくて、小沢さんとか、キクちゃんとか、なになにさんとか、そういう風に固有名詞で認識するようになってくる。そして向こうも、私のことをボランティアのあんちゃんじゃなくて、湯浅という名前で認識するようになってくるんですね。
そうすると、お互い気になりだすというか、『キクちゃん、最近見なかったな。どうしてたの?』みたいな話になるし、向こうもこっちがしばらく行かないと、『どうしてたんだ?』という話になるし、なんとなく、気になりだしちゃうというかね、匿名の一ホームレスじゃなくなるというか。
そういうことが起こりだすと、こっちも気にするし、向こうも気にしてくれたりするので、だんだん、だんだん、人間関係が密になってくるんですね。それこそ、活動の後で、路上で一緒に酒を飲んで、結局夜を明かしちゃうとか、なんかいろいろ愚痴を言われるようになって、愚痴を聞いているうちに終電を逃しちゃうとか。そういうことがいろいろ頻繁に起こるようになってくると、だんだん、だんだん、はまっていくというかね。
それで、随分、路上にも寝泊まりするようにもなりましたし、相当の人数の名前を覚えるというか、知っちゃって、その中でだんだん関係が深まっていくというのがあって、なんというか、抜けられなくなっていくという感じですかね。
山田
なるほど。最初、匿名だったおじさんたちが、身内というか親戚というか、どんな感覚ですかね?
湯浅
友達。ほんとに。ええ、友達とは名前で呼び合いますよね。名前を認識しますよね。一サラリーマンじゃなくて、○○さんですよね。そういう意味で友達になっちゃうんですよね。
山田
それで、友達が心配だから、ご飯を持っていこうとか、いろいろな支援をしてあげようということですか?
湯浅
支援してあげよう、という感じでもないんですよ。それこそ、話していると、何かの拍子でその人の傷に触れてしまうこともあるじゃないですか。ホームレスの人だって、生まれてこのかた、ホームレスだったという人はいなくて、いい時期もあったんですよね。羽振りのいい時期も。だけど、それがうまくいかなくなって、路上まで出てきてしまったわけだけど、その中には、失業があったり、離婚があったり、いろいろ傷がありますよね、その人自身の。その人自身の傷になにかの拍子に触れてしまうことがある。そうすると、話しながら、涙がぽろっというシーンもあったりして、そういうのは自分の中に深く印象に残るじゃないですか。
そして、そう話していた人が2〜3日姿が見えないと、『ちょっと何かあったかな。オレがいろいろ聞いちゃったからかな』と、そうかどうかは別にして、いろいろこっちでも考えちゃいますよね。それで、見に行くとか、会いに行くとか、そんなことをするというのは、友達関係ならあることだと思うんですよ。そういう関係になっていっちゃうという感じかな。
山田
湯浅さんは支援者という言葉に違和感はありますか?
湯浅
うーん、そうですね。通りがいいから自分でも支援者と使いますけど、少なくとも私は、ホームレスの人を救済するとか、救うとか、助けてあげるとか、そういう言葉は使わない。別にそういうつもりでやっていないから。
山田
どういうつもりなんですかね。
湯浅
一つは、自分が気にくわないからですね。こういう人が吐いて捨てられるようなね、自分が暮らす世の中として、あんまり気持ちがよくない。できれば、もうちょっと、人が吐いて捨てられないような世の中にしたい、これは自分の問題ですよね。
だから、私はホームレスの人のために活動していたという意識は全くないんですよ。自分のためにやっている。

社会活動家は、爆弾をつくる人(笑)ではなくて、「場」をつくる人。
山田
最近、湯浅さんは、「社会活動家」という肩書きでいこうとおっしゃっていますが、それはなぜですか?
湯浅
活動家って、日本ではとっても評判が悪くてですね(笑)、活動家ですっていうと、どこで爆弾作っているんですか、という感じですけど、私の定義は『場を作る人』なんです。
場というのは、色んな場があって、皆さんが作られるLe toitも一つの場です。私が今までつくって来た場も、一つの場ですよね。場を作ると人々が集まってきて、出会って、新たな関係が始まって、そこで新たな事が始まったりする。
そうやって、自分一人だと『世の中どうせ変わんねぇよな』と思っていたのが、『ちょっと、一緒になんか言ってみるか』とか『やってみるか』と、声をあげてみようかという気になる。
こういうのはエンパワーメントと言ったりしますけど、そういうことが起こるのは、場がないとできないんですね。一人一人が六畳一間のアパートでぽつねんと、全員がほか弁食ってて、その人達が全然知り合っていなくて、その中で、一人一人が『よっしゃ』って思い何かが生まれるっていうのは、あまり多くない気がする。
そうすると、場を作ることが大事で、だけど、場を作るって、いつでも誰でもできるわけでもない。『そういう場は欲しいな』っていうことはできても、どう作っていいかはわからない。その場をつくる人が活動家だって、私は言っているんです。
だから特別なことじゃない。障害者が作業所作るのも場だし、会社作るのも場だし、公民館でシンポジウムやるのも場だし、そういう場を作る人が活動家で、これは私たちの市民社会をよくしていこうと思ったら、必須のことだと思っているんですね。
避けて通れないこと、必ず必要なこと、とっても普通なこと、大事なこと、なのに、なにかすごい『あぁいうことやる人達は〜。』と別世界の人扱いされてしまうこと、それを変えたいですね。
その時に、活動家っていう言葉じゃなくて、もしかしたら『アクティビスト』とかね。横文字にした方が、通りがいいのかもしれません。だけど、自分としては、横文字にしてごまかすっていうか、話をズラすみたいなのは、できればやりたくなくて、できれば正面突破で、活動家っていうイメージの悪いものをつかいながら、その言葉のイメージを上書きしていきたい、という願いがあります。
山田
ちなみに、これ、「ソーシャルアクティビストPV」というコーナーになるんですけど(笑)
湯浅
そうですか!!(笑)しまった!
山田
いいんです、それはすごく面白いって思って。広告屋のやり方は、そうやって言葉をずらしていくんですね。そこをあえて正面突破というのが、湯浅さんのやり方ということなんですね。
湯浅
その分、確かにハードルは高くなるのでね、オレはこれで、いつまでどこまでやれるんだろうと思いながらやっていますけどね。

今やっている「場づくり」は、生活困窮者の自立を支援するネットワーク作り。
山田
最近、湯浅さんが社会活動家として手がけていらっしゃる場はどんな場がありますか?
湯浅
いろいろです。一つは全国で、こういう生活が大変な人のサポートをしようということで、小さいながらも活動を立ち上げた人達が何百とあります。そういう人達をつなげる、ネットワークする場を作りました。
山田
具体的には?
湯浅
生活困窮者の自立支援法というのが、今、国会でかかっているんですけど、これは、私が内閣府参与をやっていた時に作ったモデル事業が、いわば、ずっと恒久的な法律になるという段階になっています。
それを担うのは、全国各地の民間団体とか、すごい意識の高い市役所の人とか、そういう人達なんですが、この人達の全国的なネットワークを作るということをやったりしています。
山田
モデル事業とは、どういう事業ですか?
湯浅
私がやったのは、パーソナルサポートというモデル事業で、生活が大変な人の就労支援とか、いろいろごちゃごちゃとなっている生活の整理とかについて、福祉的なサポートと就労面のサポートを一体的にやる支援策ですね。
山田
僕もパーソナルサポートというのは知っていたんですが、ついに永続化できると。
湯浅
5年かかりました!5年かかりましたが、今法律として国会にかかっています。
山田
それが、通れば、パーソナルサポートという制度がずっと続いていくということですね。
湯浅
そうです。恒常的な制度になるので、それこそ、年金制度とか、介護保険制度と同じような制度になります。
山田
それは、本当に湯浅さんが、5年前から種をまいていたものですよね。
湯浅
長かった。最初は厚生労働省も関心持ってくれなくてね、やりたいんだったらやれば、という感じでしたけど、だんだん、3年目から厚生労働省も本気になってくれて、全国でも、『それじゃあ、やろう』という自治体も、まだまだ少ないですけど増えてきて、ようやくここに来たという感じですね。
山田
パーソナルサポート、まだみんな、知らない方もけっこうたくさんいると思うのですが、困窮者の就労支援とか、人それぞれに応じたサポートを提案して寄り添って支援していくというイメージですか。
湯浅
伴走型とか、寄り添い型と言ってきましたけどね。寄り添うという言葉は、東日本大震災で相当広がり、寄り添うという考え方や発想が必要なんだ、と言われるようになったけど、私たちは前の年にそのモデル事業を立ち上げて、寄り添い型支援、伴走型支援ということを言ってきたんですね。
今回の東日本大震災の被災者の方に限らず、どんな人でも、いろいろな大変な目にあってきた人には、その思いや悩みを聞くという寄り添い型のサポートがないと、『こうすりゃ、いいじゃねーか』と言ったところで、実際そういう風にはならないんですよ。そういう意味で効果がない、そういう支援は。なので、ちゃんと効果があがる支援をしようと。効果があがる支援をすることが、社会的にもプラスを生み出す。その人が働いたり、いろいろな形の担い手になったり。そういう意味で社会にとって得することだと。
単に心優しいから、負担が増えてもしょうがないよね、ということではなくて、心優しいことが、社会的にもプラスになると。こういうことを訴えてきて形になってきたということですかね。

『地縁』、『血縁』、『社縁』がなくなってしまった日本には、新たな『縁』が必要です。それがソーシャルインクルージョンの発想。
山田
どうして今の日本にパーソナルサポートのような支援が必要になってきたと思われますか?
湯浅
これは、無縁社会の問題なんですけど、日本社会は基本的に家族『血縁』ですね、それから、地域『地縁』ですね。特に男性はですが、会社『社縁』、この3つで何らかの縁を持ってきた人達が大多数だったんですよね。
それで、この『地縁』、『血縁』、『社縁』が、3つともないと『無縁』と言われる。『無縁』というのは『地縁』、『血縁』、『社縁』がないということです。地域は相当疲弊してきてしまった。家族もかつてほどの力は持たない。核家族化してきたし、家族の中でもかなり思いがバラバラだったり。会社も、かつての家族みたいな会社は、今もあるが、減ってきてしまった。もうちょっとドライな、『使えるだけ使うけど、使えなくなったらごめんね』と、そういう感じになってきた。
そうすると、かつての縁を担っていた、『地縁』、『血縁』、『社縁』がかつてほどの力を持たなくなってきた時に、私たちは、新たな縁を作らなければならない。その新たな縁が、いわば地域や家族や会社に替わる、寄り添ってくれる人。それが、家族にも地域にも会社にも居ないのだったら、社会的に作っていかなければいけない。そうじゃないと、その人の具合が余計に悪くなって、余計にコストがかかるようになったりしてしまう。そういうものを作っていこうというのが、パーソナルサポートの発想ですね。
山田
それはつまり、ソーシャルインクルージョン。
湯浅
そうですね、我々は社会的包摂といいますが、英語で言うと、ソーシャルインクルージョン。日本語訳が定着していないので『社会的包容力』と訳されることもありますけど。ようするに、皆が参加することで、多くの人が担い手になって、それで社会をまわしていこうという発想です。
日本は高齢化も世界一ですし、人口も減っていっています。そういう中で、担い手の分母は減っていかざるを得ないのですね。今まで担い手の60パーセントしかなかったのを、70パーセントあるいは80パーセントにしないと、社会はまわらなくなっていく。
そういう意味で、高齢者、障害者、ニート、フリーター、引きこもり、ホームレス、生活保護受給者、貧困者、性的マイノリティー・LGBT、DV被害者、そうした人達を、『おまえは俺たちと違うからダメだ』と言って排除しないで、その人たちも担い手になってもらわないと社会はまわらない。今、日本社会はそういうところに来ているということですね。

山田
はい。まさに私たちはそれをお伝えしたくてLe toitを立ち上げました。
216万人の生活保護受給者の「想い」を顕在化したい。
山田
もう一つ、湯浅さんが今始められている、生活保護受給者の思いを顕在化する活動がありますが、今なぜそういうことをやろうとしているのか、語ってもらえますか。
湯浅
これは私の推測ですが、生活保護ってあんまりイメージが良くなくて、どっちかっていうと不正受給が一杯あるんじゃない?というイメージがかなり一般的じゃないかと思うんですよね。
そのイメージを変えたいと思った時に、あまり良くないイメージの典型は、役所の前におじさんたちが列をなしてね、顔にはみんなモザイクが入っていて、荷物をけっこう一杯持っていて、役所が開くとわーっと一斉に中に入っていって、次のカットはカウンター越しにお金をやりとりするカットがあって、その次はパチンコ屋の資料映像みたいな。そういう映像が、この3年ぐらいテレビとかでも頻繁に流れてきたと思うんです。
そういうイメージがもし、人々の中に入ってしまっているとすると、別のイメージを持ってもらわないことには、冷静に話ができない。じゃあ、別のイメージを持ってもらいたい時に、やっぱりそれが、顔にモザイクかかっていたり、匿名だったり、Aさん、みたいな話だとやはり印象に残らないので、そのイメージに上書きされないと思っています。
だからこそ、生活保護の利用家庭で育った若者とかが、実名と顔出しで、ちゃんと出て自分のことを話す、というようなものを媒体や雑誌として作れないかな、と思ったのが最初です。それが、『生活保護』という、人を非常に感情的にするテーマを冷静に議論するために必要なことかな、と思っているんですね。それで作り始めました。
山田
雑誌の名前は?
湯浅
『はるまち』というのですが、季刊雑誌です。はるまちというのは、すみれのような、ハルマチソウという花の名前ですけど、春を待つっていうかね、もうちょっと人目を気にせず生きられるというか、普通の人として受け入れてもらえることを待つ、願う、というイメージですね。
山田
編集において、顔を出すという事はなかなか難しかったと思いますが、その辺はどうですか。
湯浅
それは今でも難しいです。表紙を利用者本人の顔で飾るわけですが、なかなか、なり手を探すのが大変ですね。それは当然で、実際にこの間創刊号を出したのですが、2ちゃんねるでスレッドがたって批判がおこるわけですよ。
本人が何を言おうが、どんな人だろうが、生活保護というだけで、批判する人はいるんですよね。だから、しょうがない。だけど、しょうがいないということを本人が腹くくるというのは、なかなか経験してみないとわからない。多くの人は、自分がそういう立場に立ったことがないから。
そういう意味でリスクが高いんですね。だから私は表紙候補になる人に『やめろ!』というくらいの勢いでそのリスクを話しています。これは私的には苦しいことなんですけど、本当は出てほしいんですよ。出た結果、こんなはずじゃなかったと本人が思ってしまったら、本人にとっても、私にとっても不幸ですから、『こういうことが起こるよ』とさんざん脅します。さんざん脅して、それでも出ると言った人に、出てもらうようにしているので、やっぱりハードル高いですよ。
山田
しかも出演された方は何才ぐらい?
湯浅
創刊号は21才の男の子。物心ついた時には、家庭が生活保護を受けているので、本人たちには選択のしようがないですよね。だけれど、ある種の後ろめたい思いは持っていて、友達に言っていないんですよね。だけど、今はそこからぬけて、自分で働いて暮らしていて、そういう中で、どういう思いを持って、いったいいつ、自分の家に金がないことに気づいたのかとか、生活保護ということをどう自分なりに受け止めて整理していたのかとか、そういうことはほとんど伝わっていないと思うんです。
でも、今生活保護を受けている人って、216万人いるんですよ。子供が30万人います。子供が30万人いて、その30万人の顔が全然見えていないというのは、これでは、やはり冷静な議論はできない、と感じるんですね。
山田
音声も変えられて、おかしいなと思いますよね。
湯浅
変えられる。でもマスメディアにとっては、本人を守るためで、実際それでテレビ局とかにクレームが来ますから。だからモザイクかかるのは、ある意味、やむをえないことなんです。どれだけ覚悟のある人をさがすか、どれだけ当事者とつながるネットワークがあるかということにかかってくるので。
山田
Le toitでは、セクシュアルマイノリティの方に顔出しでご出演いただき、カミングアウトをした時のエピソードを語っていただく企画があるんですが、かなり難航しています。
湯浅
難航しますよね。
山田
でもお話をきいていると、オネエ系タレントさんたちの活躍のおかげで、だいぶカミングアウトしやすくはなったって聞きます。思いきって仲間に言ってみたら、男女両方から恋愛相談を受けるようになったとか。
湯浅
だいぶ社会の理解は、LGBT(レズ・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジャンダー)に関しては高まってきたと思うんですけど、個々を見たら、すごく偏見の強い職場とか、偏見の強い家庭というのはあるんです。だからカミングアウトする人からすると、これで仕事を失うかもしれないとか、これで家族から後ろ指さされるかもしれないリスクを背負うということになるので、それは本人にとっては相当な勇気なんですよ。
LGBTの今の日本社会におけるポジションは、生活保護の人たちとよく似ていると思います。とても偏見が強くて、気持ち悪いと言われたり、そういう中でカミングアウトするには、恐ろしく勇気がいるというね。

高度経済成長をもう一度みたいな雰囲気に違和感がある。50歳が20歳になろうとしている感じ。これは長続きしないだろうと。
山田
突然ですが、最近の日本ってどうですか?
湯浅
一番違和感もっているのは、高度経済状況復活みたいなモードになっていることですかね。オリンピックも来ますしね、リニアモーターカーも走るし、なんとなく、あの頃の、三丁目の夕日の頃の日本社会をもう一度と、ノスタルジーが日本の中を覆っているかな、と感じるんですけど、それは私はあまり健全なこととは思えない。50才が20才になろうとしているような、無理に無理を重ねているイメージがあってですね、これは長続きしないだろうな、と思っています。
そういう意味では、50才なりの成熟の仕方、20才じゃないのだから、もう20才の時のようには出来ないけれど、でも50才には50才なりの成熟の仕方があるわけで、それを社会的に確立するというか、持っていくというか。それが例えば、コミュニティ重視のライフスタイルとか、Uターン、Iターン組で田舎暮らしを始めたり、都会でシェアハウスしたりして、ものすごく収入は高くないけど、そんなにコストもかからない生活もしながら、仲間と一緒に楽しく暮らして行くというライフスタイルもあったり。
かつてみたいな、いつかはクラウンという価値観じゃなくて、カーシェアリングでもいいから自分たちで車が使えるとか、必要な時に使えればいい、そういう価値観が一時期相当広まったと思っています。今でもそうですけど。
でもこの1〜2年ぐらいは、『やっぱりそれじゃダメだよね』というモードになってきて、『やっぱりオリンピックだ、やっぱりリニアモーターカーだ、やっぱり経済成長だ。』という話になって、揺り戻してきた。
だけど、これは長く続かないだろうから、カンフル剤を打って走っている50代みたいなもので、カンフル剤が切れたあとに余計疲れるんじゃないか、余計疲れきった自分が鏡の前にいるんじゃないか、という気がしてすごく心配です。
山田
今、安倍さんが『世界で一番企業が活躍できる国にする』って言っていますが、その辺はどうですか?
湯浅
いいんですけどね、別に。企業が活躍しやすい国っていうのが、何を意味しているか、ってことですね。企業が活躍しにくい国よりも活躍しやすい国の方がいいと思いますよ。だけど、そのために働く人がいろいろ我慢しないといけない、いろいろ捨てないといけない、ってことになると本末転倒になっていくだろうな、と思うんですね。
企業さんが活躍する国になぜしたいかというと、最終的には働く人に余裕を持たせたいからですよね。家計に余裕があって、みんなが安心して消費が出来て、子供が育てられて、という世の中にしたいから、企業さんが活躍できる国にしたいと言っているわけですけど、なにか、そのために働く人たちが我慢しなさい、という感じになってきていますよね。
そうすると、自分の豊かさのために、自分の豊かさを我慢する、みたいな話になってしまって、いったい何がやりたいんだ、という本末転倒ぶりが出てくるんですよ。これは、私たちの社会にはよくあることで、私はよく言うんですけど、日本の会社員のお父さんたちというのは、家族のために家にいないんですよね。
長時間労働をしている。家族を食わせるために、会社でずっーと働いている。これはいったい、家族のためなのかどうなのかと、よくわからなくなってくる。
そういう家族のために、家族を不在にする、というような逆転した逆立ちしたようなことが、今回の話の中でもあります。働く人や暮らす人たちが豊かになるために、暮らす人たちが我慢しなければいけないと、なにかそういう話になってきて、いわゆる小泉改革の時は、今我慢して将来の豊かさを手にいれるんだ、って言われて、結局、みんな我慢したけど、豊かさは来なかったんです。あれの二の舞にならないか、ということが心配ですね。
山田
企業は儲かりましたね、当時。
湯浅
当時だいたい企業平均で、5年間で1.7倍。企業収支は2倍近くになりました。だけど、働く人の賃金は全体として微減、下がりましたから。それはもう、企業さんが儲かったからって、働く人が潤う時代では、もはやない。だって、リストラした会社の方が株価があがるんだから。
そういう意味では、もうそういう時代じゃないのに、高度経済成長期のイメージがありますよね。会社が豊かになれば、自分たちも豊かになれる。このイメージは、戦後日本の唯一、最大の成功体験だから、『もう、そういう時代じゃないんだ』と私みたいな人がわかった顔で言っていても、全然、響かないんですよ。
自分たちが初めて冷蔵庫を持った時の、初めて炊飯器を買った時の、初めてカラーテレビが家に来た時の、あの実感に私の言葉は勝てない、そういうことだと思います。
山田
それが今の政権を選んでいる、みたいな感じですね。
湯浅
その夢をもう一度ってモードですよね。それはもう、民主党政権の失敗もあって、ああいうのはうんざりだと、いうこともテコになって働いていますが。
山田
企業が儲かってもそれは労働者には行かないんじゃないか、むしろ、もっともっと過酷な状況になる可能性があるとすると、今、せっかく湯浅さんが、新しく法制化をはかっているパーソナルサポートとか、社会的に排除された人たちをどう支えて、もう一回社会参加させようかという流れの中で下地が出来てきているのに、もう一回振り出しに戻ってしまうような感じがするのですが、いかがですか。
湯浅
心配していますね。特に心配しているのは地方なんですけど、東京から遠いところほど、この10年は、こういう感じになってきた。そういうところは、どうやって今までお金をまわしてきたかというと、公共事業と企業誘致だったんですよね。。
公共事業と企業誘致というのは、両方、その地域にとっては外から来るものです。公共事業は中央政府から来るものだし、企業誘致というのは東京や大阪の本社さんから来るものだし、そのために地域にいて出世するには、中央との太いパイプをアピールするような人が出世していたんですよね。。
それが今までの日本社会の伝統的な地域のあり方を決めていたのですが、10年くらい前から、もうそうではなくなってきちゃったんですよ。。
そうすると、いくら中央との太いパイプを強調しようが、公共事業はこない、いくら言ったって企業はこない、という状態にだんだんなってきて、その中で、地域が何に気づいてきたかというと、外頼みじゃだめだということに気づいてきたんですね。。
外から来てもらうのを待っていてはダメだと、じゃあどうするか、自分たちに今ここにあるものを見直していかないといけない。キャッチフレーズ的にいうと、『ないものねだりしてもしょうがない』って。『あるもの探しをしよう』という発想になっていった。。
その中で、例えば、このうちの漁港からあがってくる魚や貝の中には、商品価値がないといって捨てられるものがあると。だけど、この貝をなんとか、商品価値を見いだせないか、という風に工夫したり。。
あるいは、おじいちゃん、おばあちゃんが山から採ってきたキノコを、ありがたいと思っても食っていなかったけど、ここからなんとか成分を抽出して、健康茶を作るとすごくいいんだ、とかね。そうやって商品化していこうとか。。
あるいは、古い街並みをリノベーションして、地域の特産品を置いたりすると観光客が一杯来るとか、あるいは太陽光や、風力や地熱や、この土地に照っている太陽や吹いている風とか、地面にある熱とか、そういうものを利用していこうと。。
ようするに、ここにあるもの、人、モノ、自然で、この地域を成り立たせていかないと、『外からなんか来てくんねーかな?』じゃ、もうダメなんだ、っていう風に10年間腹をくくってきた、と思っているんです。
そういう中で、失敗は一杯しながら、ちょっとづつ成功事例がたまってきて、こういうあり方が地域の中で出て来た。その中で、人の活性化もあってね、ニートや引きこもりだと言って、どんどん切り捨てていたら、地域はもたないので、ただでさえ高齢化率は、30パーセント、40パーセントなんだから。若い人が一人でも二人でもいたら、その人に頑張ってもらおうじゃないか、と言う風に発想して、切り捨てるんじゃなくて、担い手になってもらうという風に、腹をくくってきたと思っているんですよ。
それが、『そんなしんどいことやらなくても、もう一回中央に陳情に行けば、公共事業が来てくれるんじゃないか』とか、『もう一回、元気な企業が出て来たから、企業誘致で工場を作ってくれるんじゃないか』とか、そういう、ちょっと先祖返り的なモードになって、今まで、せっかく積み上げてきた内発的な内側からの発展ということを、もう一回ひょっとしたら忘れちゃうということがありゃしないか、ということを一番心配しています。

企業が儲かったからといって、働く人が潤う時代ではもはやない。
山田
雇用の流動化についてはどうですか?
湯浅
世界的に見ればデンマークやオランダが有名ですけど、雇用を流動化させる時には同時に雇用を失う人が増えるということなんだから、そのセーフティーネットを強化するということがセットにない限り、無理なんですね。流動化したからと言ってみんなしがみつきますから。だって失業したら生活が大変なんだもの。
ということは、失業できる社会にする、ってことなんです。雇用を流動化させるということは。失業しても生活が苦しくない社会にする、ということを意味しているんです。だけど、失業しても生活が苦しくならない国にするっていう、その部分は今は残念ながらないですね。
そうではなくて、流動化する事で異動がしやすくなって、いわば成功した転職組の話がスタンダードになっている。でも、転職して成功する人って実は多くないですよ。そういう意味では負の部分もあるんですけど、それは言わない。
成功している人は、どんな時代、どんな状況だっていますから、その人たちがスタンダードだと言えば、逆にそうならない人は努力が足りなかったんだよね、という話で終わってしまう。その理屈は、ないと思います。
山田
そういう人たちが、新自由主義とか、規制緩和する人たち、より民間へ民間へと、労働は雇用自由化、そして流動化していこうという流れが、盤石な支持のもとというか議席的には支持を得ているわけですが、そうじゃない視点で、湯浅さんが今やろうとしていることや、ソーシャルインクルージョンの考え方、そしてパーソナルサポートの話など、もっともっと世の中に違う価値を知ってもらうためにはどういう風にしたらいいですか。
湯浅
こういう風に言ったり考えたりすることが、まっとうだしかつ格好いい、という風にならないといけないでしょうね。そういう意味でLe toitのような社会問題をクリエイティブのスキルを使ってわかりやすく伝えていくようなメディアはとっても大事だと思っています。
つまり、お父さんは、家族のためにと言って家にいないんじゃなくて、家族のためにと言うなら、家にいたらいいんですよ。
でも、家にいたら、なんかこう、経済成長ができなくなっちゃうんだとか、会社が発展しなくなったら元も甲もない、とか、そんないろいろな理屈をつけて結局家族のために家にいないという選択をせざるを得ない。これでしょうがないんだと、みんな言うんですけど、いや、しょうがなくないんだと。
そういうことが、今現実味を持って受け取れないんですよ。『おまえはそう言うかもしれないけど、そんな綺麗事を言ったって、世の中済まないんだ』とかね、『世の中はそういうもんじゃないんだ』とか、そうやって、現実感を感じられないんですよね。
だから、あんまり自分もいい事だと思っていないけど、現実的にはそれしか選択肢がないんだと思っちゃっている訳です。そこは、別の、今話してきたようなことの選択肢がより現実的になるためには、やっぱりこっちの方がクールだっていう感じにならないと、なかなか広がらない。正しいか、正しくないか、というだけでは世の中は動かないですからね。
そういう意味では、正しくかつクールだという風になるための、あの手この手が必要だと思います。
山田
社会活動家のイメチェンをしていこうというお話がありましたが、具体的にはどんな感じでイメチェンをはかるのですか?
湯浅
一つは、これが特別なことではない、普通のことだ、普通に必要なことだ、というような価値観を広めるということと、もう一つは、そういうことをやっていることが格好いいという風にならないといけない。そのためには、私も含めてそれを担っている人たちが、格好よくならないといけない、そう思っていますね。
山田
最近、スタイリストも?
湯浅
ねぇ、大変なことですよ、私にとっては。革命的なことです。本当に。(笑)
山田
意識してやられているわけですよね。
湯浅
いっちゃあなんですけど、私、服のセンスないですからね。言われたものを着ているだけなんですけど(笑)。でもだいぶやっぱり、印象は違うみたいです。相当。あまり怖そうじゃなくなったと、最近よく言われます。そういう意味では、こういうのも大事だなぁと、つくづく思いますね。










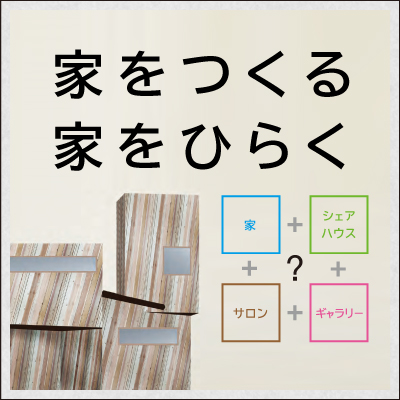

![隣人[LGBT]100人のカミングアウト](../images/banner/banner_rnjn.jpg)